求人広告代理店事業TOP > お役立ちノウハウ > 高度人材とは?計算方法や優遇措置を解説
高度人材とは?計算方法や優遇措置を解説
 こんにちは。求人広告代理店・採用代行の「株式会社ONE」です!
こんにちは。求人広告代理店・採用代行の「株式会社ONE」です!
「高度人材」という言葉は、近年頻繁に耳にするようになりました。
しかし、具体的にどのような人材を指すのか、どのような基準で認定されるのか、そしてどのような優遇措置が受けられるのか、明確に理解している方は少ないのではないでしょうか。
このページでは、高度人材の定義や認定基準、優遇措置について、わかりやすく解説しています。
高度人材制度を理解することで、自社の採用戦略や人材育成に役立てていただければ幸いです。
「高度人材を受け入れると何が良いの?」や「制度が複雑で受け入れをためらっている」、「3種類の高度人材の区別がつかない」などといった方もぜひご覧ください。
今すぐ、理想の人材に出会う
採用を成功させる
『3つの方法』をお伝えします
※同業者・競合企業様は資料ダウンロードはご遠慮いただきますよう
お願いいたします。
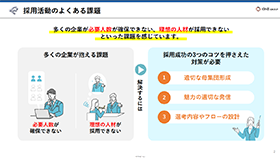
目次
高度人材とは、高度な専門知識や技能を有し、日本の経済社会の発展に貢献する可能性の高い外国籍人材です。
平成21年5月29日に公開された「高度人材受入推進会議報告書」では、『高度人材とは、「国内の資本・労働とは補完関係にあり、代替することが出来ない良質な人材」であり、「我が国の産業にイノベーションをもたらすとともに、日本人との切磋琢磨を通じて専門的・技術的な労働市場の発展を促し、我が国労働市場の効率性を高めることが期待される人材」』 と定義されています。
日本では「高度人材ポイント制」を導入しており、高度人材の活動内容ごとに条件を設けてポイントを付与しています。
ポイントの合計が一定点数(70点)に達した場合などに、高度人材の優遇措置を受けられる仕組みです。
高度人材は活動内容によって、以下の3つの種類に分類できます。
※出展:出入国在留管理庁
それぞれ解説します。
「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う研究、研究の指導又は教育をする活動」が該当します。
具体的な該当職種は、
などです。
高度学術研究分野の認定要件には、最低年収基準が設けられていません。
そのため、ポイントが70点以上あれば申請が可能です。
研究に重きをおいた分野であるため、研究実績のポイントは高めに設定されています。
「特許の発明」や「入国前に公的機関からグラントを受けた研究に従事した」などの実績に2つ以上に該当する場合、1つあたりのポイントが20点から25点に引き上げられるのが特徴です。
「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動」が当てはまります。
具体的には、
が対象となりやすいです。
理系または文系分野における大学で習得するレベルの、一定水準以上の専門知識や技術を持っていることが求められます。
ポイントの合計が70点以上であり、年収が300万円以上の場合のみ高度人材としての認定申請が可能です。
高度専門職1号(ハ)に申請できるのは、「本邦の公私の機関において事業の経営を行い又は管理に従事する活動」を行う外国人材です。
具体的には、
などが当てはまります。
高度専門職1号(ハ)には最低年収基準があり、申請要件を満たすには年収が300万円以上かつポイントが70点以上あることが必要です。
経営や管理に関わる職種のなかでも、代表取締役や代表執行役取締役、執行役に就任している場合には、ボーナスポイントが加算されます。
経営する事業に1億円以上の投資を行っている場合は追加ボーナスがあるなど、高度専門職1号(ハ)ならではの加算ポイントがあるのが特徴です。
「高度専門職1号」を取得後、一定期間(3年)以上在留するなどの条件を満たすと「高度専門職2号」が取得できます。
指定の活動内容(イロハ)を行った外国人材が取得対象で、高度専門職1号と2号の違いは優遇措置です。
「高度専門職2号」の方が、在留期限が無期限となるなど、より多くの優遇措置を受けられます。
高度人材ポイント制は、平成24年5月7日から導入された制度です。
高度人材の受け入れを促進するためにスタートした制度で、ポイント制を用いて出入国管理上の優遇措置を決めます。
優遇措置を受けるには取得ポイントが合計70点を超えることが条件です。
評価項目は、
などがあります。
これらを総合的に評価し、合計ポイントが計算されるのです。
計算方法や加算される条件は活動内容によって異なるため、最新の内容は出入国在留管理庁が公開している「ポイント計算表」から確認しましょう。

引用:出入国在留管理庁「ポイント計算表」
「高度専門職1号」と「高度専門職2号」とでは受けられる優遇措置に違いがあります。
具体的な優遇措置の内容をご紹介します。
「高度専門職1号」の場合に受けられる優遇措置は以下のとおりです。
どの優遇措置も通常の在留資格より条件が緩和されているのが特徴です。
それぞれ詳しく解説します。
通常、外国人は1つの在留資格で認められている活動しかできません。
「高度専門職1号」の在留資格があれば、複数の在留資格にまたがっての活動が可能です。
例えば、「大学で研究を行いながら、関連事業の経営に携わる」といった活動が認められます。
基本的に在留資格によって認められる在留期間は異なります。
「高度専門職1号」の外国人材であれば、法律上最長である「5年」の在留期間が一律付与されます。
在留期間の更新も可能です。
外国人が日本で永住許可を得るためには、原則として「10年以上日本に在留していること」が必要です。
「高度専門職1号」の在留資格を有していると、この永住許可要件が緩和されます。
出入国在留管理庁が公開している「永住許可に関するガイドライン」では詳しい緩和条件が確認できるので確認してみましょう。
具体的には、以下の場合に在留歴に係る永住許可要件の緩和措置を受けられます。
原則では10年間の在留が必要ですが、ポイントが高ければ1年間の活動で、永住許可を受けられるようになるのが高度人材ポイント制の大きな特徴です。
通常は「配偶者」の在留資格を有する外国人が日本国内で活動をする場合は、該当の在留資格を取得する必要があります。
そのため、配偶者であっても活動内容に合わせた学歴や職歴といった要件を満たすことが就労の条件です。
一方、高度人材の配偶者の場合は、学歴や職歴などの要件が求められません。
要件を満たしていなくても「教育」や「技術・人文知識・国際業務」といった在留資格が必要な活動を行うことができます。
原則として、外国人が就労を目的に在留する場合、親の帯同は許可されません。
しかし、高度人材に限っては所定のケースに当てはまり、かつ一定の要件を満たすとき、高度人材本人か配偶者の親の入国と在留が許容されます。
具体的には、高度人材またはその配偶者の7歳未満の子(養子含む)を養育する場合や、高度人材の妊娠中の配偶者または妊娠中の高度人材本人の介助等を行うケースです。
主な要件として、
があります。
家事使用人の雇用は、在留資格が「経営・管理」「法律・会計業務」などで在留する場合でしか認められていません。
しかし高度人材の場合、一定の条件下での家事使用人の帯同が許容されています。
主な要件は、
などです。
「高度専門職1号」は在留期間が5年となりますが、期間の更新も可能です。
そのため、入国事前審査と在留審査の処理が優先的に行われます。
処理にかかる日数の目安は以下のとおりです。
「高度専門職2号」は「高度専門職1号」に比べると、在留期間と活動制限が緩和されるのが特徴です。
具体的な優遇措置は以下のとおりです。
就労に関する在留資格には、
があります。
「高度専門職1号」とは異なり、転職をした場合に在留資格を変更する必要はありません。
ほとんど制限なく、日本国内での就労を続けられるのが「高度専門職2号」の特徴です。
今すぐ、理想の人材に出会う
採用を成功させる
『3つの方法』をお伝えします
※同業者・競合企業様は資料ダウンロードはご遠慮いただきますよう
お願いいたします。
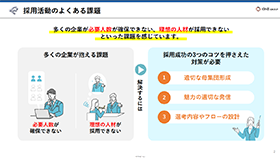
高度人材として認定を受けるためには、所定の方法で申請手続きを行いましょう。
申請手続きは、新規手続きか変更申請かによって、申請方法が異なるため注意が必要です。
ここでは、新規の場合と変更の場合の2パターンにわけて、高度人材の申請手続きの方法を解説します。
新規申請を行う外国人材はまず、地方入国管理局に「在留資格認定証明書(COE)」の交付を申請します。
必要書類は、
です。
高度人材を受け入れる企業が本人に代わって申請することもできます。
次に行われるのは、提出書類をもとにした出入国在留管理庁による審査です。
ここで実際にポイントが計算され、ポイントが70点以上になると高度専門職として認められます。
審査は優遇措置の対象となるため、申請受理から10日以内を目安に回答を得られるでしょう。
審査の結果、在留認定がされると、高度専門職「1号(イ・ロ・ハ)」のいずれかの在留資格が付記された「在留資格認定証明書」が交付されます。
在留認定証明書の送付先は、外国人材本人か代理機関です。
外国人材の居住国にある日本大使館でビザの申請(査証申請)を行います。
申請完了後、ついに日本への入国ができるようになります。
ビザ発行までの期間は条件によって異なりますが、出入国在留管理庁公表の「在留審査処理期間(日数)」によると、審査期間は14.4〜24日です。
外国人材が入国する際に利用する日本の空港、または港で上陸審査を受けます。
在留認定証明書と査証が貼られたパスポートを提示することで得られるのが「在留カード」です。
すでに日本に在留している外国人の場合、在留資格の切り替えや更新が必要です。
高度専門職のビザの更新は「在留資格変更許可申請」、高度専門職への切り替えは、「在留期間更新許可申請」を行いましょう。
申請を受けて、入国在留管理庁が審査をします。
審査のポイントは以下の3つです。
ポイント70点以上かつ在留資格の種類ごとの要件を満たしていると、在留資格認定証の交付を受けられます。
今すぐ、理想の人材に出会う
採用を成功させる
『3つの方法』をお伝えします
※同業者・競合企業様は資料ダウンロードはご遠慮いただきますよう
お願いいたします。
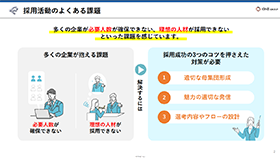
日本は高度人材受け入れに積極的です。
ポイント制の導入時に掲げていた「2020年末までに高度人材10,000人受け入れ」は達成され、現在も受け入れは拡大しています。
その背景には、世界各国で起きている最先端の知識や技術を持つ人材の獲得競争があります。
2023年4月には、トップレベルの人材確保を目的に「特別高度人材制度(J-Skip)」が導入されました。
日本は世界水準の技術力や生産力を持つために、積極的に高度人材受け入れに取り組んでいるのです。
高度人材の受け入れは、日本の経済成長を促進させる効果があります。
企業が高度人材を採用することで、
といったメリットを享受できるでしょう。
特に、国際化が進む現代においては、外国語や外国文化に精通したグローバル人材の存在は欠かせません。
今後さらに激化する国際競争で日本が競争力を維持するためにも、高度人材の受け入れ促進が重要視されていくでしょう。
高度人材受け入れのためにポイント制や優遇措置を講じている日本ですが、いくつかの課題を抱えています。
JETROが発表した「我が国の高度外国人材受入と課題」によると、日本が抱える課題は大きく分けると以下の2つです。
外国人留学生の約65%が日本での就職を希望しながらも、実際に就職したのは35%に留まっています。
これには、ジョブ型の雇用形態を前提としている外国人と、メンバーシップ型の日本企業との間に認識の差があることが理由に挙げられます。
さらに、日本的な同調圧力による多様性の抑制も高度人材の定着を妨げているといえるでしょう。
また、高度外国人材の89%が都市部に集中しているため、地域への定着も課題のひとつです。
グローバル化が進む社会のなかで企業がより発展していくためには、高度人材を積極的に活用することが効果的です。
高度人材の採用を検討されている場合は、人材採用の実績豊富なONEをご活用ください。
人材採用はもちろん、タレントマネジメントや各種研修など、人材に関する業務を一気通貫でサポートいたします。
まずはお気軽にお問い合わせください。
高度人材の受け入れは日本が積極的に取り組んでいる施策です。
3種類の「高度専門職」のいずれかで認定されると、在留期間や配偶者および親の帯同許容など、さまざまな優遇措置を受けられます。
申請方法の違いや「高度専門職1号」と「高度専門職2号」の違いを理解して、企業の成長に役立つ高度人材の採用を検討してみてはいかがでしょうか。
採用手法16選と最新トレンドを紹介!選び方や求人募集のコツも解説
採用手法16選と最新トレンドを紹介!選び方や求人募集のコツも解説
応募が来ない原因と対策
求人募集しているのに応募が来ない3つの原因と対策
その他、今日から使える採用ノウハウやあらゆるお悩みが解決できるコンテンツをご用意しています。ぜひご参考にしていただければと思います。
中途採用
面接・採用
Instagram採用