求人広告代理店事業TOP > お役立ちノウハウ > 採用ブログとは?始めるメリットと投稿したい内容を解説
採用ブログとは?始めるメリットと投稿したい内容を解説
 こんにちは。求人広告代理店・採用代行の「株式会社ONE」です!
こんにちは。求人広告代理店・採用代行の「株式会社ONE」です!
人材採用の手段として、求人広告や採用サイトを活用している企業は多いですが、より自社の魅力を知ってもらう方法として、採用ブログへの注目が高まっています。
担当者が自由に更新できる採用ブログは、リアルタイムな情報を、自由に発信できます。
採用ブログは、社員紹介や仕事風景など、さまざまな視点から発信できるため、自社のファンを増やし、採用へつなげられます。
今回は、採用ブログを始めたい企業さま向けに、始め方や運営のポイント、投稿ネタなどについて解説します。
無料『Instagram運用支援サービス』資料ダウンロード
\ 運用方法がわからない方必見 /
人材採用のプロが採用に特化した
Instagram運用を徹底サポートします!
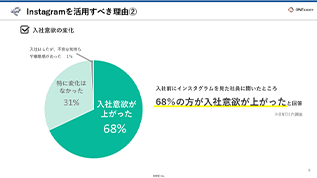

※同業者・競合企業様は資料ダウンロードはご遠慮いただきますようお願いいたします。
目次
採用ブログは人事ブログとも呼ばれ、求職者に対して情報を提供するツールです。
採用サイトや会社説明会だけでは伝えきれない自社の魅力を、ブログという形で発信します。
日々更新されるブログを閲覧することで、求職者は自社への認知を深め、応募の動機づけへとつなげていきます。
採用ブログとは?始めるメリットと投稿したい内容を解説 TOPへ
企業側が使う主な採用手法として、求人広告や採用サイトなどがありますが、それだけでは伝えきれない情報もあります。
採用ブログなら、担当者次第で自由に情報発信できます。
選考スケジュールや会社説明会、インターンシップなど採用選考に関する情報はもちろん、日頃の社内風景などを、制限なく発信できます。
新卒・中途問わずフランクな形で情報提供するツールとして、活用できます。
採用ブログとは?始めるメリットと投稿したい内容を解説 TOPへ
採用ブログを運営する目的はいくつかあります。
その中でも、求職者に自社への好感を持ってもらい、入社意欲が増すようなツールにすることが大切です。
そのためにも、自社への応募意思を持った求職者がスムーズに採用サイトを閲覧できるように、採用ブログにリンクを貼っておくなどの工夫が必要です。
情報収集している求職者に、数ある企業の中から自社を認知してもらうためのきっかけとなるものです。
企業の内情が見えると、求職者は親近感を抱きます。
特に、長い期間をかけて就職活動する新卒の求職者は、コンスタントに更新される採用ブログを読むことが習慣化して次第にファン(愛読者)になっていきます。
企業理念や事業概要だけでなく、社員の仕事風景やインタビューなどが掲載されていると、求職者は「この会社で働きたい」「この人たちと一緒に仕事をしたい」と感じるようになり、入社意欲が増します。
自社への応募意思を持った求職者が、正しく自社への理解を深め、応募動機を形成する手助けとなります。
採用ブログとは?始めるメリットと投稿したい内容を解説 TOPへ
働き方が多様化した現在、求職者が企業に求める条件は、待遇や給与だけではありません。
自社の採用ブログでカジュアルダウンした企業を紹介すると、採用サイトや求人広告だけでは伝わらない魅力を発信できます。
採用サイトや求人広告だけでは、限られた情報しか届けられません。
一方、採用ブログは運営内容を自社で決められますし、更新するタイミングも自由です。
社内イベントの様子や社員インタビューなど、生きた情報をより多く発信できます。
採用ブログを運営することで、入社後のミスマッチや内定辞退などを防ぎます。
求職者は、採用ブログを見ることで自分とマッチする会社かどうかを判断し、入社希望の意識を深めていきます。
また、採用ブログで内定者を紹介すると、企業の一員と感じてもらいやすくなるため、正式入社までの間に帰属意識も芽生えます。
選考中の学生も内定を得た先輩のリアルな声に触れることで、自社への興味関心がさらに高まるでしょう。
採用ブログは、コーポレートブランディングの形成も可能です。
通常は、プレスリリースやコーポレートサイトなどでブランディングを行いますが、採用ブログもその一端を担います。
ブログ内で自社の企業理念やコーポレートニュースを継続的に発信していくことで、求職者だけでなく、将来のクライアントからの閲覧も見込まれます。
自社の存在意義や価値観を知ってもらうチャンスとなるでしょう。
採用ブログでは、求人広告や会社説明会だけでは伝えきれない、自社のフランクな情報を発信できるため、効果的な母集団の形成に繋がります。
自社にマッチした求職者を十分な数確保できることは、採用活動においても有効性を発揮します。
採用ブログとは?始めるメリットと投稿したい内容を解説 TOPへ
採用ブログを始める場合、いくつか自社で決めることがあります。
以下のステップを踏むことで、開始後もスムーズに採用ブログを運営できます。
まずは、運営の担当者を決めます。
採用ブログは採用人事だけでなく、広報としての側面も持ち合わせているため、責任者は人事担当だったとしても、複数の部署から運営に関わるメンバーを募りましょう。
記事の作成は、複数の部署が持ち回りで行ったり、書けるときに書ける人が更新をしたりなど、いろいろな方法があります。
コンスタントに更新することがブログの価値を高めるので、ブログのネタ出しには多くの社員から協力を仰ぐことが重要です。
次に、作成メディアを決めます。オウンドメディア内に作る、採用系サイトの外部サービスを利用するなどの方法があります。
オウンドメディア内に作る場合は、サイトデザインから始めましょう。
自社のカラーを全面に打ち出せるので、コーポレートブランディングにも役立ちますが、一から作成するためコストがかかります。
外部サービスを利用する場合は、すぐに更新をスタートできます。
サイト制作のコストがかからず、求職者の目に触れる機会も多いため、母集団の形成に役立つのがメリットです。
ただし、既存のデザインを利用するので、自社のオリジナルカラーを出すことは難しくなります。
発信するテーマの内容は自由度が高く、運営のアイデア次第で変わります。
「社風を伝えたい」「社員の個性を全面に出したい」「コーポレートブランディングにつなげたい」など、自社の方針を決定してから発信しましょう。
多角的な視点から、自社の魅力をアピールできるように工夫することが重要です。
【発信テーマの参考例】
文字だけでなく写真を取り入れることで、社内の雰囲気がより求職者に伝わりやすくなります。
採用ブログは、継続的に更新し続けることがポイントです。
自社のブログを認知した求職者(読み手)は、頻繁にチェックするようになるため、コンスタントにブログを更新すると、求職者の興味関心が長期間持続します。
一方で、「毎日更新する」と決めたばかりに、頻度だけを重視して内容が中途半端なものになってしまうと、逆効果になります。
発信する情報がフローではなくストックコンテンツになることを忘れずに、内容へのこだわりも重視しましょう。
採用ブログとは?始めるメリットと投稿したい内容を解説 TOPへ
採用ブログを運営していくときに労力を費やすのが、ネタ探しです。
求職者の視点に立ち、有益な情報を発信することを念頭に置いて考えましょう。
ブログでは、自社HPや会社説明会だけでは伝わらない、日々の社内風景を映し出せるようにすることが重要です。
更新を重ねていくと、「読まれる記事」「読まれない記事」が分かってくるので、まずは継続的に更新することを目標にしましょう。
日頃から採用ブランドが伝わる情報を発信しているなら、それもネタになり得ます。
自社のHPに掲載している場合も多いですが、採用ブログではより深堀りし、分かりやすいものにします。
インタビュー形式や対談形式などにし、読みやすく工夫をするのもよいでしょう。
企業トップから経営方針や事業戦略について直接聞けるため、求職者に伝わりやすくなりますし、多忙な経営陣の負担を最小限に抑えることも可能です。
自社の社風を紹介して、求職者に雰囲気や特徴を伝えましょう。
全社アンケートの結果を掲載すると、職場の実態が伝わりやすくなります。
企業文化は、全社共有の価値観や行動規範を指します。
人事担当がコラムを書いたり、複数人が対談形式で紹介したりすると伝わりやすいです。
自社で行う資格や検定のサポートなど、社員の成長をサポートする制度を紹介しましょう。
社内で、サポート制度を活用した経験のある社員にインタビューし、どんなタイミングでどのように活用したのか聞き取りましょう。
サポート制度が全社に行きわたっていない場合もあるので、社員にとっても有益な情報になり得ます。
社員が日頃働いている様子は、求職者にとって興味のある内容です。
「一日の流れ」でもいいですが、昼休憩の様子が伝わるようなものも良いでしょう。
また、自社においてのオフィスカジュアルなども、実際に写真で掲載されていると伝わりやすくなります。
社員へのインタビューは、採用ブログの定番ネタです。
各部署やプロジェクトごとなど、できるだけ多くの社員にインタビューしましょう。
その際のポイントは、一貫したテーマを持ってインタビューすることです。
企業理念をベースにテーマを決めるといいでしょう。
インタビューする社員のピックアップもしやすくなりますし、企業理念を伝えやすくなります。
インタビュー記事を読んだ求職者が「自分もこの人と一緒に働きたい」と思えるような内容を心がけましょう。
インタビューは対面で行い、後日文字起こしするパターンと、回答を本人に書いてもらうパターンがあります。
【インタビュー内容の例】
採用に関することはもちろん、自社で開催しているイベントレポートを掲載しましょう。
通常、社内でのイベントは外からはなかなか分からないので、求職者にとっては有益な情報になります。
自社の企業風土や雰囲気を知ってもらうためにも、入社式や表彰式、忘年会や社員旅行などの様子を積極的に載せましょう。親しみがわき入社意欲が向上します。
異業種からの転職組や未経験の求職者に、業界内部にいるからこそ教えられる勉強法を紹介します。
勉強法は、転職者向け、新卒向けなどに分けて紹介してもいいでしょう。
個人ブログで紹介されるような内容を採用ブログに掲載すると、有益性が高まります。
新卒採用を考えている場合は、新入社員に一年間密着した記事を書くのもおすすめです。
求職者にとって大変参考になる内容なので、入社したての頃から研修期間、配属先が決まった後など、時系列でまとめて定期的に密着の様子を更新しましょう。
自社サイトで紹介している製品やサービスの紹介ではなく、違った視点からも紹介しましょう。
例えば、自社製品を活用しているクライアントへ取材し、生の声を届けるといったアイデアが考えられます。
求職者だけでなく、社員にとっても勉強になるコンテンツなので、製品が商品化されるまでの開発秘話などを紹介するのも、リアルな仕事現場の発信になります。
自社製品やサービスの勉強会があった際には、その様子をレポートするのもいいでしょう。
テーマを決め、それに沿って多くの社員にコラムを書いてもらう方法があります。
運営担当者だけがブログを作成していると、どうしても偏った記事になってしまうため、さまざまな部署で働く人の視点から記事を書いてもらいましょう。
社員が内容を書く分、運営担当者の負担も軽減しますが、社員が自由に書ける分、企業のブログとして発信する基準に達しない場合もあります。
そのため、運営担当者のチェックは必須です。
採用ブログとは?始めるメリットと投稿したい内容を解説 TOPへ
自社にマッチした人材確保のために、採用ブログの活用は有効です。
人事的な視点を持ちつつも、採用に直結するコンテンツに偏ることのないようにしましょう。
「いずれブログ全体が採用に繋がるコンテンツに成長すればいい」といった長期的な視点で臨みましょう。ここでは、運営上のポイントについてご紹介します。
常に新鮮な情報を発信するために、更新頻度はある程度高くすることがポイントです。
途中で更新が途絶えたブログほど、求職者に良くない印象を与えるものはありません。
こういった事態を防ぐためにも、運営者は人事だけでなく複数の部署から出すことが大切です。
採用活動の繁忙期などで人事担当がブログを更新する余裕がないときは、他部署の担当者がフォローするなど、臨機応変に協力し合いましょう。
コンスタントに更新できない場合、採用ブログ自体の削除も検討するべきでしょう。
文字だけのブログよりも、写真や動画があるブログの方が読みやすく、親近感を覚えます。
職場の風景や社員の仕事の様子、イベント開催時の様子などを文字と一緒に掲載すると、よりリアルな自社の雰囲気を伝えられます。
可視化することで、求職者側のミスマッチ防止にも有効です。
自社での実際の働き方を発信します。
時短勤務やリモートワークなど複数の働き方があるなら、それらを記載しましょう。
実際にその働き方をしている社員にインタビューしたり一日のスケジュールを紹介したりするのもいいでしょう。
「求職者だったら何を知りたいか」といった目線で情報発信しましょう。
求職者は「説明会で質問するには気が引ける」「質問するほどのことではない」と考えて、質問を断念してしまうことが多いです。
そのため、求職者が欲する情報をブログで発信していくと、効果的な母集団の形成に繋がります。
採用ブログのネタ出しには、全社員からの協力を仰ぎましょう。
自社の仕事を網羅した形で情報発信するには、運営担当者だけがネタをピックアップするやり方では限界があります。
運営メンバーのネタ出し会議の際には、各部署から集めたアイデアを発表してもらうなど工夫しましょう。
ネタ出しの協力ではなくても、社員の日報や各部署の会議の議事録を閲覧することで新しいアイデアが出てくるかもしれません。
採用ブログとは?始めるメリットと投稿したい内容を解説 TOPへ
採用ブログは、自社の社員の協力を得ると、負担が少なく求職活動ができるツールのひとつです。
「採用ブログというツールを初めて知った」という企業も、「採用ブログに興味はあったが始めるのに二の足を踏んでいた」という企業も、採用ブログのメリットを知ったことでブログ運営のハードルが下がってきているのではないでしょうか。
自社の魅力を自由に発信し続けることで、求職者への認知を拡大させ、ファンにすることができます。
求職者の応募意欲向上に役立つため、ぜひ自社で運営する採用ブログを検討してみましょう。
採用ブログとは?始めるメリットと投稿したい内容を解説 TOPへ
採用手法16選と最新トレンドを紹介!選び方や求人募集のコツも解説
採用手法16選と最新トレンドを紹介!選び方や求人募集のコツも解説
応募が来ない原因と対策
求人募集しているのに応募が来ない3つの原因と対策
その他、今日から使える採用ノウハウやあらゆるお悩みが解決できるコンテンツをご用意しています。ぜひご参考にしていただければと思います。
中途採用
面接・採用
Instagram採用